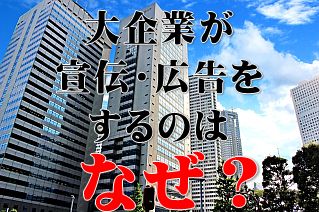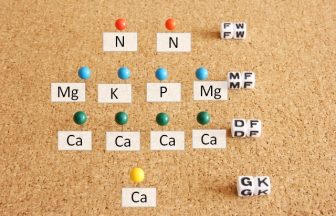農薬を使うとか使わないとか、肥料をどんなものにするかとか、どんな栽培をするのかは
出来たものを誰に売るのか
によって大きく変わります。
食の安全を気にする主婦なのか、味にこだわるレストランのシェフなのか、珍しいものが欲しい八百屋なのか、とにかく安く仕入れたい卸業者なのか。
売り先が決まらないとどんなものをどのように育てたらいいのか決まりません。
そして次に。
売り先つまりターゲットが決まり、そこに向けて売る作物を育てるため栽培方法を決めます。
農薬は使うのか、使わないのか。
肥料は化学肥料なのか、有機肥料なのか、それとも無肥料なのか。
耕すのか、耕さないのか。
畝を立てるのか、立てないで平畝にするのか。
どんな資材(ビニールマルチ、ネット、不織布、ビニールトンネルなど)を使うのか。
どのように選択して栽培方法を決定するのか、それはターゲットによります。
ターゲットが必要としている農産物を提供するために、どんな栽培方法が必要なのかを考えて、そして選択する。
ということです。
でもその前に。
まずは物事の本質を知っておく必要があります。
なぜ農薬がいるのか。
なぜ肥料がいるのか。
なぜ耕すのか。
それを頭で理解して、腑に落ちていてようやく、栽培方法を決めることができます。
なぜ農薬を使わなければいけないのかを知らずに農薬を使う人はいません。
肥料を入れるのはなぜかを知らないまま肥料を散布する人はいません。
耕すことの意味を知らずに、なんとなく耕していると大きな失敗をすることになります。
今回は。
なぜ耕すのかについて詳しく書いていきます。
書かれていることに間違いがあったり説明が不十分だったりするかもしれませんが、なぜ耕すのかを考えるきっかけになればと思います。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
耕すことにどんな意味があるのか
土を耕すことの効果はいろいろあります。
いくつかを挙げて簡単に説明していきますが、詳しく知りたければ専門的に解説した書籍が山のようにありますのでそちらをご参照ください。
大きな効果としてよく言われるのが養分の放出作用。
土を耕して撹拌し、空気を入れることで土中微生物の活動が活発になります。
そうすると土に含まれている有機物の分解が進んで、作物の栄養となる成分が放出されます。
ただし。
化学肥料では微生物が肥料を分解しなくても植物の根はそれを吸うことができますが、有機肥料では微生物がそれを分解して有機態から無機態に変えることでようやく植物の根が吸える状態になります。
だから、化学肥料を多投する農業よりも有機肥料を使った農業において耕すという行為が非常に大切なものになってくるようです。
これに関連して乾土効果(かんどこうか)がありますが、今回は触れませんので興味のある方は調べてみてください。
もうひとつ。
耕すことの効果として植物の根張りがよくなることが挙げられます。
土がほどよくほぐされていると、根はスムーズに伸びていくことができます。
根がよく張っている植物は、人間でいえばよく運動していて健康的な状態ですから、根を張りやすい土を作っておくことは重要なことです。
ただし。
耕さなくても根はしっかりと張れる、ふわふわな土に張った根は弱いので健康的とは言えない、耕さないときの植物の初期生育は遅いが最終的には耕したときの植物に追いつく。
といった意見もありますので、根張りのために耕すというのは注意が必要です。
ではここで。
耕すということを別の視点で見てほしいと思います。
まずは耕さない状態を想像してみてください。
あくまで自然な状態。
よほどの天変地異でなければ、人が手を加えずに放っておけば草が生えて木が生えて、
物理的にも化学的にも生物的にも安定した状態を保っています。
平和的、と表現してもいいかもしれません。
そこへ野菜や米など作物のタネを播く、苗を植えるとどうなるでしょうか。
平和的で調和が保たれているところへ外的な侵入者が入ってくる。
というのがタネを播く、苗を植えるという行為です。
安定しているところへ侵入してもそこに根付くことは難しい、ということがお分かり頂けるでしょうか。
入り込む余地がない、といった感じです。
もし耕さないで作物を育てようと思ったら、地表面の草になんらかの処理をするとか苗を大きめに育てておいてから植えるとか、それなりの措置が必要になります。
では次に。
耕したときのことを想像してみてください。
物理的にも化学的にも生物的にも安定した状態を、一気に混ぜて壊す。
天変地異を起こして混乱を引き起こす。
というのが耕耘という行為です。
そこにあった平和は消え去り、土の中はまさに混沌。
それまでにあった常識が消え去り、固定概念がなくなり、世界が変わります。
耕すというのは、そこに住む生き物にとっては天変地異に等しい行為なんです。
そこへ野菜や米など作物のタネを播く、苗を植えるとどうなるでしょうか。
耕した直後はあまりにも混沌としすぎていますが、しばらくして混乱がすこしおさまってからだったら、外的な侵入者が入り込む余地があります。
根付くのも比較的簡単です。
ド田舎(不耕起)に引っ越すときには地元住民の強固な和があるため入り込むのが難しいですが、混沌とした都市(耕起)に引っ越してきてもそこに住み着くのは簡単。
ということ。
耕された土の状態は、雑多な感じの都市に似ているのかもしれません。
明治維新を見れば耕すことの意味が見えてくる

(画像参照:幕末・維新風雲伝)
耕起と不耕起。
耕すことでなにをもたらすのか。
これについて人間社会の例を当てはめてみると意外にしっくりきます。
江戸時代。
徳川幕府による安定した統治で、国内は平和だったといえます。
急速な発展などは望めませんが、ゆっくりと着実に成長・発展を続けていきました。
そこへやってきたのが白い肌をした諸外国勢力。
ヨーロッパの小さな国々が、世界中の多くの国々を植民地化してきた時代です。
日本は鎖国をして限られた国とだけ貿易をしてきましたが、植民地政策の魔の手がついに日本にも襲いかかってきました。
でもここで日本は屈しなかった。
世界中のほとんどの国々が敗北し植民地化されていく中で、日本は果敢に立ち向かっていきました。
それができたのはなぜか。
長く続いた江戸時代に、ゆっくりとではあるけど蓄積してきた国力があったから。
外敵によって混乱が起きたときに、その蓄えていた国力を放出することができたから対等に戦うことができたんです。
この流れ。
江戸時代から明治維新を経て、明治時代に入っていく流れ。
耕すという行為にすごく似ています。
江戸時代というのは耕されていない状態です。
安定的であり平和的。
そこに外的な圧力がかかります。
明治維新です。
諸外国がやってきて日本を混乱にひきずりこむのは、土を耕して混沌とした状態を作り出すことに似ています。
つまり諸外国勢力=耕耘。
外敵によって混乱が起きたときに、日本は蓄えていた国力を放出しました。
土は混乱によって、蓄えていた養分を放出します。
その後、日本は文明開化によって急速な発展を遂げましたが、土も耕耘することで全く違った状態に変化していくことになります。
なぜ耕すのかはお客様が決める
江戸時代のほうがいいとか、明治以降の日本は素晴らしいとか、そんなことを言いたいわけではありません。
どちらが正しいということではなくて何を望むのかが重要です。
江戸時代に育った人、昭和という時代で育った人。
お客様がどちらの人を好むのか。
不耕起で育てられた作物を望んでいるのか、耕起された土で育てられた作物を望んでいるのか。
お客様の要望を知り、それに応えるために耕すのか耕さないのかを判断すべきだと思います。
そのためには。
耕さないで育てることでどんな作物ができるのか、どんな味になるのか。
耕して育てることでどんな作物になるのか、どんな味になるのか。
そもそも耕すという行為は作物の味に影響するのかどうか。
それらを知る必要があります。
耕すとはどういうことかを理解して、自分には耕耘が必要なのかを判断してみてください。
多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?
たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。
このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。
そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・
このときすでに、じつは大きな間違いをしています。
有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?
有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。
「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」
と、収入は二の次だと言います。
だからこそ見えなくなっていた真実。それは、
有機農業はちゃんと稼げる
ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。
ただし、条件があります。
それは・・・