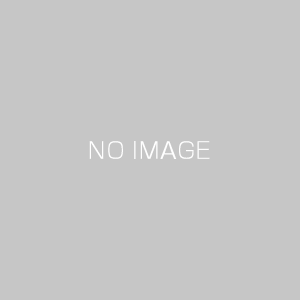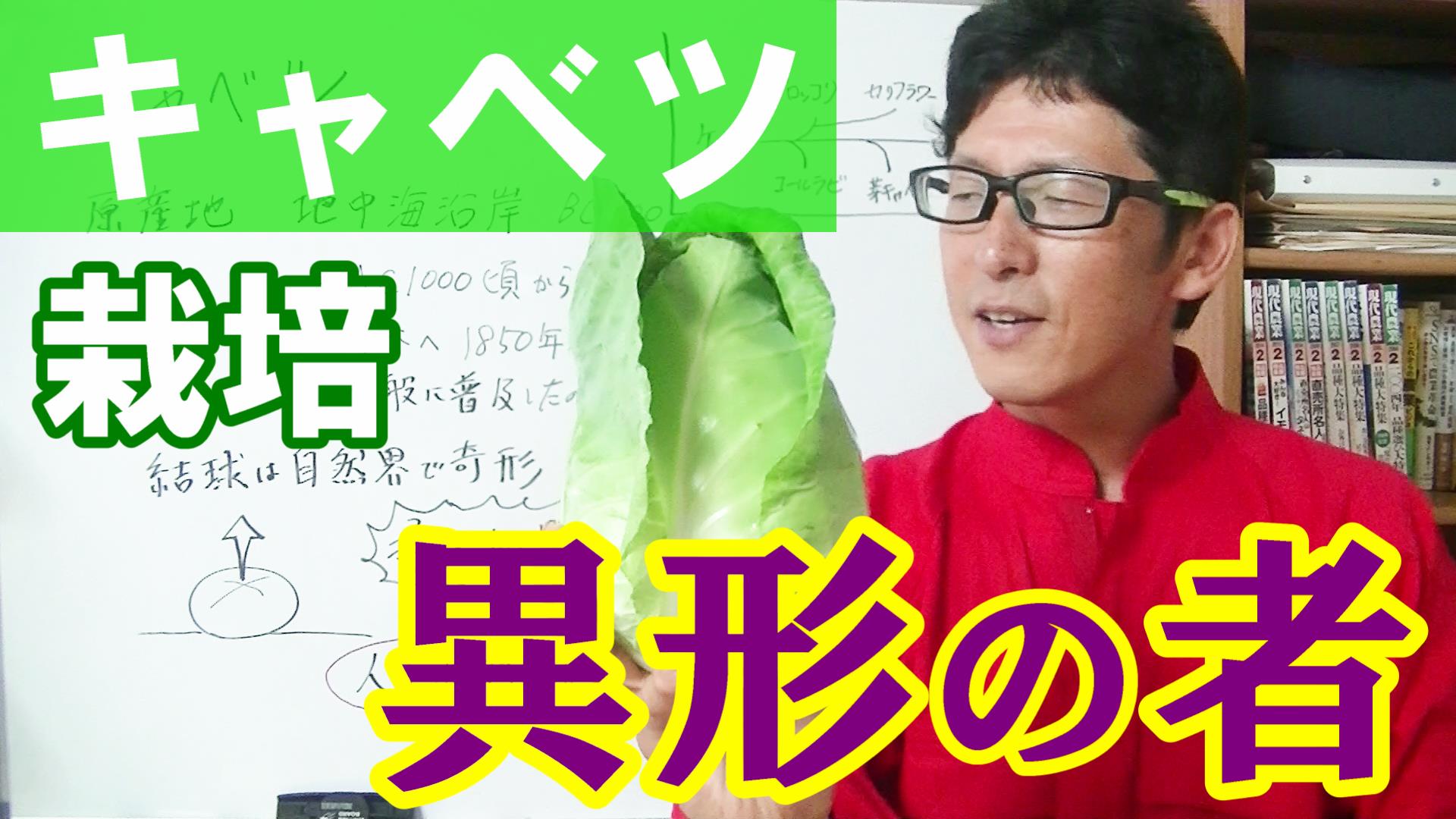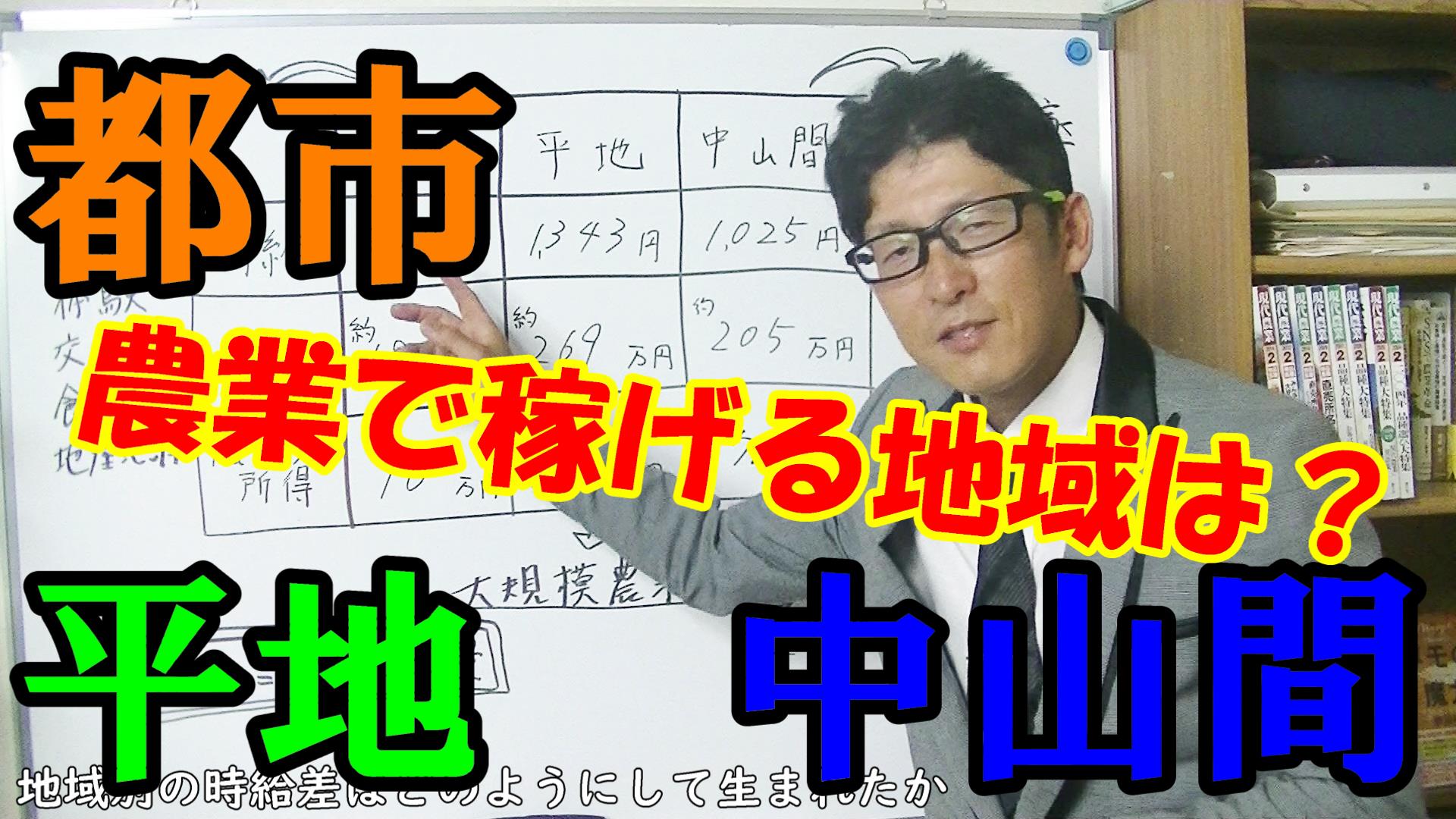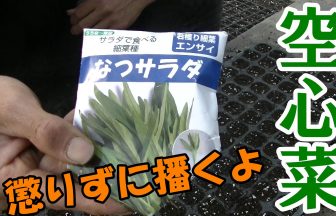研修生にはほとんどの農作業を経験してもらうようにしています。
種まきひとつとっても、耕して、畝を立てて、溝を切って、タネを播いて、覆土して、鎮圧して。
と様々な作業が組み合わさっています。
そこに土壌条件(土質、粉砕度合い、湿り具合など)や種まき前後の天候を考慮しながら種まき時期を決めていくわけで、それらひとつひとつを言葉で伝えるのは容易ではありません。
各要素の組み合わせなどを考えると無限にあるので、とてもじゃないけど伝えられません。
たとえば溝を切るとき、土質が粘土質なのか砂質なのかによって覆土の量が違うのでそれに合わせた溝の深さにしなければならないし、野菜の種類によって種の大きさや適切な覆土量が違うのでそれも考慮する必要がある。
さらに言えば、適切な覆土ができるような溝の切り方をすると作業効率があがるなどの労働に関するポイントも外せない。
溝きりだけでもこれだけのことを考えてやっています。
こういうのは体験して学んで初めて身につくものです。
本を読んでいても得られるものじゃありません。
研修生には今のうちに経験を通して成功・失敗してもらって、就農してからスムーズに栽培をしてもらいたいと思いますね。
僕は研修を受けてから就農した人間ですが、畑に直接タネを播くことが多い葉もの野菜については学びが少なかったこともあって就農当初はかなり苦労しました。
タネを播いたのに全然発芽しない、発芽にばらつきがある。
そんなことはしょっちゅうでした。
だから就農1年目2年目あたりは葉もの野菜が多い春とか秋が嫌いで、苗を植えることが多い夏野菜に気持ちが偏っていました。
でも今では直播きのほうが好きになってきています。
目の前にある畑でいろいろと試しながら、数多くの失敗を乗り越えてきたからこその変化です。
僕の農園で失敗してほしくないけど、失敗から学ぶことは多いので研修生にはどんどん失敗を重ねて欲しいと思いますね。
その失敗を吸収できるような体制をつくっていくのが当面の僕の仕事になりそうです。
ひゃ~ひとりで全部やるより数段難しいぞ。
多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?
たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。
このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。
そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・
このときすでに、じつは大きな間違いをしています。
有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?
有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。
「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」
と、収入は二の次だと言います。
だからこそ見えなくなっていた真実。それは、
有機農業はちゃんと稼げる
ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。
ただし、条件があります。
それは・・・