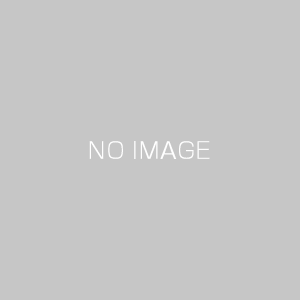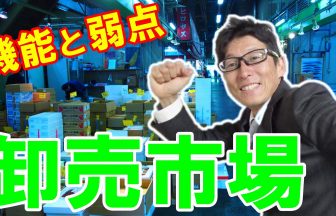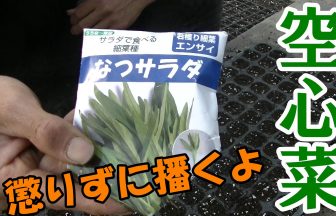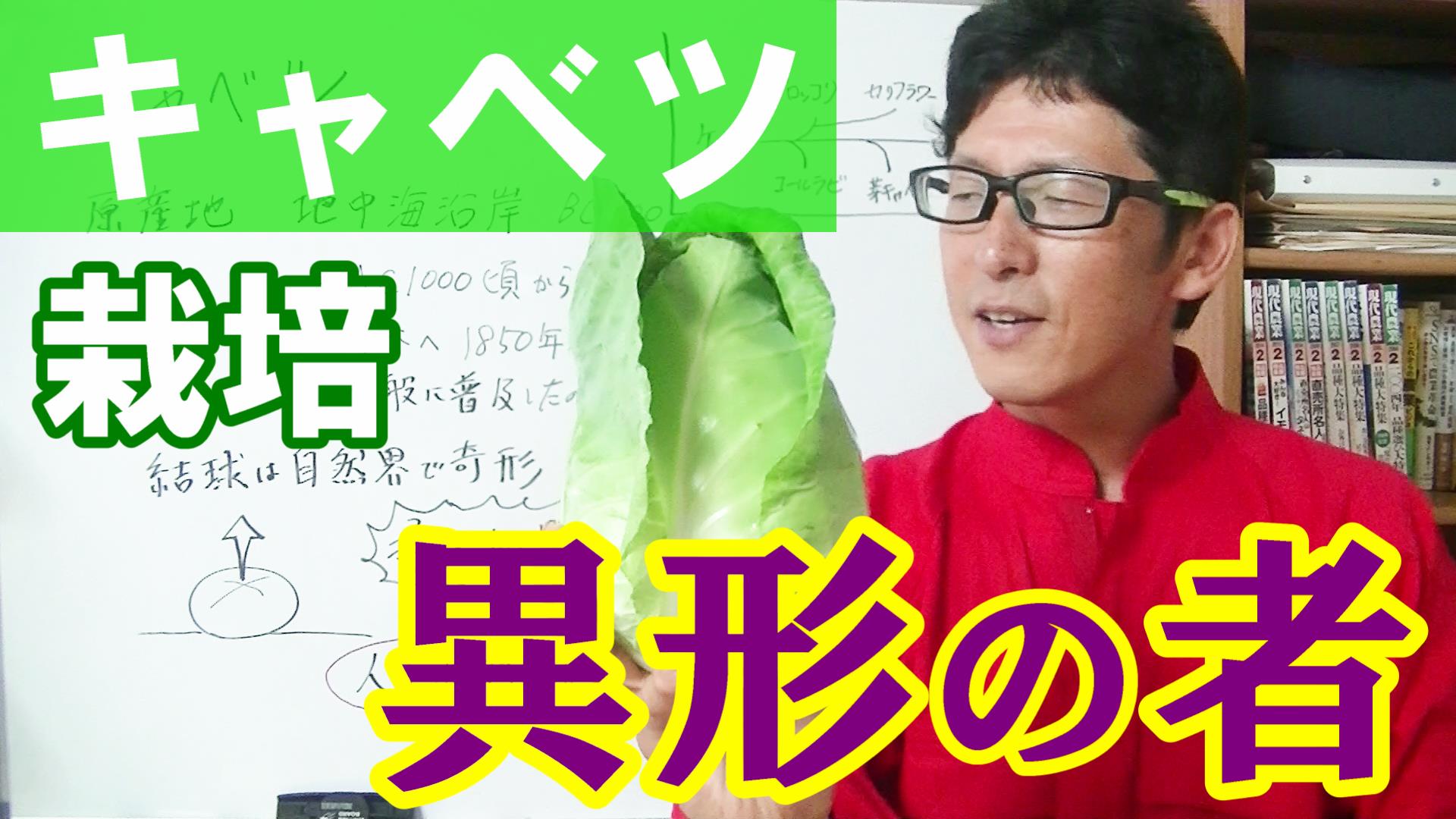農業では年間を通すと労働のピークになるところが必ず出てきます。
稲作なら田植え時期と収穫時期。
野菜や果樹はたいてい収穫時期にピークが来ます。
ここ松平の特産「七草」なんて年末年始にものすごいピークがあります。
このピークという制約に対処する方法は主にみっつ。
1、ひとりでできる労働には限界があるので、ピークになるところに合わせて作付け量を制限する。
2、ピークのときにだけ雇用を増やして対応する。
3、年間通してピークをなるべくつくらないように品目を組み合わせる。
といったところでしょうか。
一般的に、多品目少量栽培は有機農業の特徴の一つと言われているので、労働のピークへの対応としては3番が主流だろうと思います。
うちもそうしています。
それでもやっぱり夏もしくは初秋にピークがくるし、冬は基本的に暇だし、なかなか労働時間は平らにはなりませんね。
なだらかな丘のようになればいいなぁなんて思うんですが。

2010年がわかりやすかったのでグラフ化しましたが、12~4月(農閑期)と5~11月(農繁期)にはっきり分かれていますね。
これから4月末くらいまではあんまり忙しくないシーズン。
農閑期を堪能します。
もちろんやるべきことはやりますよ。
多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?
たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。
このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。
そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・
このときすでに、じつは大きな間違いをしています。
有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?
有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。
「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」
と、収入は二の次だと言います。
だからこそ見えなくなっていた真実。それは、
有機農業はちゃんと稼げる
ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。
ただし、条件があります。
それは・・・